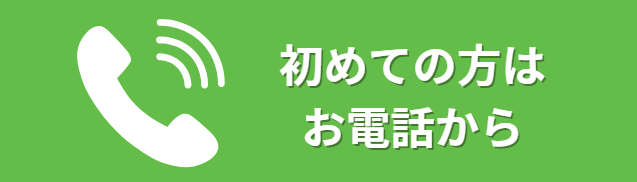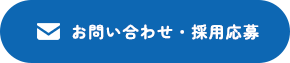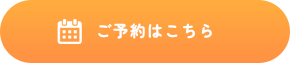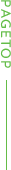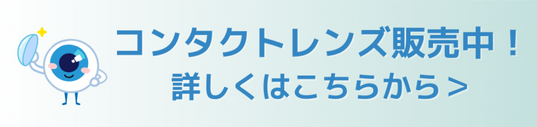子供が近視かも…!?神奈川県・座間市で年々増え続けている子供の近視の原因や近視抑制の方法・対策について2025.02.28 ブログ

本を読むときやタブレットを使っているときなど、子供が物に“近づき過ぎている様子”を見せることはないでしょうか。
生活環境が昔と変わり、日頃から目を酷使する機会が増えている昨今。子供たちの視力が低下傾向にあることは、社会問題にも発展しています。
これから長い人生において“見え方”はとても大事なことです。視力が低下した場合はそのまま放置せず、早めに対策をすることが大事です。
今回は、近視と分かったら近視抑制をおすすめする理由や、近視を進行させない生活環境などについてお話していきます。
当院で行っている小学生高学年から開始できる近視抑制の治療もご紹介しますので、ご参考ください。
子供のための近視抑制とは?
はじめに、近視の仕組みと症状、近視を引き起こす要因について見ていきましょう。
そもそも“近視”の症状とは?
“近くが視える”という文字からも分かるように、近視は近くの物に焦点が合って遠くがぼやける屈折異常のことです。
私たちの物の見え方は、
・角膜、水晶体を通って目に入った光が屈折することでピントが合う
・それが「角膜」に映し出される
という仕組みにより、“映像”として見ることができます。
近視になると、網膜までが長くなり、奥行きのある目になります。網膜よりも手前で焦点が合ってしまうため、遠くのものがぼやけてしまうのです。
近年増え続けている子供の近視
数十年前と比較すると、早いうちから視力が低下する子供が年々増えています。
現代は、学校でもプライベートでも目を使う機会が多いです。家庭ではパソコンやタブレット、ゲームなどがほとんどの家であるのではないでしょうか。授業でもタブレットが導入されているケースは多いですよね。
また、子供達同士の遊び方も昔とはずいぶん変わってきました。学校から帰宅すると公園の遊具で遊ぶ、草むらでボール遊びをする…など、太陽の下で体を使った遊びが主流だった昔。
対して現代は、ゲームやパソコン、タブレット、スマホというように屋内で画面を見ながら“目を使う遊び”が普通です。のめり込むように画面を眺めていると、まばたきも少なくなり、酷使された目は疲労していることも多いでしょう。
こんな子供の様子があったら近視かも…
子供の視力が悪くなると、
・ゲームやテレビに顔を近づけ過ぎている
・目を細めて見るときがある
・勉強するとき机と顔の距離が近い
・まばたきが頻繁
などの様子をよく見せます。
近視になる主な原因

子供の近視の主な原因として考えられるのは「遺伝性のもの」と「生活環境によるもの」です。
たとえば、「両親どちらかが近視・両親ともに近視」というケースでは、「両親どちらも近視ではない」という子供と比べて近視になるリスクが高まります。
ただ、最近は多くの子供達の生活環境が“近視を引き起こしやすいもの”であることから、遺伝的要素よりも生活環境が背景にあるという考えが強まっています。
進行が早い子供の近視
子供の近視は、“成長期”とも重なっていることから、大人よりも進行が早いです。小学校高学年にもなると子供の身長はどんどん伸びて体も大きくなる時期。眼球も伸びて広がるため、近視がさらに悪化するメカニズムです。
子供の近視は何歳ごろから?
近視が発現するのは、小学生や中学生くらいが多い傾向です。
ゲームやタブレットを長時間する、1日中家の中で過ごす、背が伸びそれに伴い眼が大きくなる事など、様々な要因から近視の進行が早まります。
最近は就学前の子供達でもタブレットやゲームを使うケースが増えているので、小学校入学前から近視が見られることもあります。
近視が将来的に目の病気を発症させるリスクにつながる
子供の近視は、「軽度だろう」と様子見されることもあります。
最近では、子供の近視が将来的な目の病気にも影響を与える可能性が指摘されています。病的な近視になると、単純にメガネやコンタクトなどでは見え方が改善できない病気になる可能性もないとは言えません。
目は一生使い続けなければならない大切なものです。子供時代の近視を放置することが、将来的な視力の悪化や場合によっては失明につながり、日々の生活の質を低下させてしまう可能性もあります。
気になる症状があれば、できるだけ早めに眼科受診をすることが大事です。
近視の種類と当院での近視抑制方法
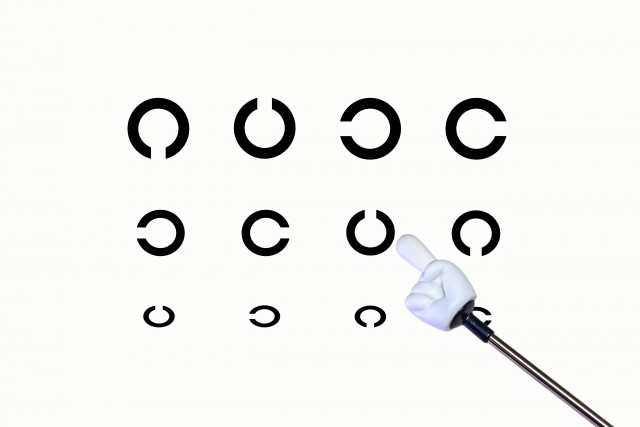
近視にはいくつかのタイプがあります。
「近視」には種類がある
近視は「軸性近視」と「屈折性近視」、「仮性近視」とに分けることができます。
軸性近視
軸性近視とは、角膜から網膜までの長さ“眼軸長”が伸びたことが原因で起こる近視です。
目の形が楕円形に細長く変形し、網膜の位置が後ろにずれることで遠くをぼやけさせてしまいます。多くの方の近視は、この軸性近視です。
基本的に成長期に生じるため、放置してしまうと最悪の場合、病的な近視に繋がります。眼軸が伸びてしまった場合、元に戻すのは不可能です。
屈折性近視
屈折性近視は目の形は変形しませんが、角膜のカーブや水晶体の屈折力が強まり、本来焦点となるはずの網膜よりも手前に焦点がずれてくる状態の近視です。
仮性近視
仮性近視(偽近視)は、目のレンズである水晶体を動かすための「毛様体筋」が過度に緊張して起こる近視です。一時的な近視ですが、状態を放置すると“仮”ではなく本当に近視になってしまいます。
当院で行える子供の近視抑制治療のご提案
当院では、近視のお子様に「点眼薬を用いた近視抑制」の方法をご提案しています。
子どもの近視は回復できる?視力低下をおさえるための対策とは
遠くの物を見えづらそうにしている子供の様子を見ると心配ですよね。近視が回復できるか気になるところではないでしょうか。
近視は回復する?
近視の大多数である軸性近視は、眼球が変形して奥行きが長くなって起こっているため、治すことはできません。
ただし、眼科で受ける治療や生活習慣に気をつけることなどで近視の進行を抑制できます。
また、近視の種類のうち、一時的な状態である「仮性近視」は視力を回復できる可能性があります。
いずれにしても、眼科受診で目の状態をきちんと確認し、適切な治療を受けることが重要です。
視力低下をおさえるための具体的な対策
次は、視力が低下しないための具体的な対策についてご紹介します。
物を見るときは離れて正しい姿勢で
教科書やタブレットに近づき過ぎて視力が低下することも多いので、離れて見るように親御さんが声をかけてあげましょう。
また、ソファーに寝ながら見るなど、姿勢の悪さも視力の低下につながります。
明るいところで勉強や読書をする
暗い部屋で目を使う作業をすると、目に力が入り負担です。勉強や読書、パソコン、タブレットなどは、周囲が明るい環境で行うようにしましょう。
目の休息が重要
勉強やスマホなどで「ずっと同じ画面を見続ける」と目に負担がかかって視力が低下します。ときどき、目を離して“休息”を取りましょう。
外の光を浴びる
屋内の暗いところに長くいると、視力が低下し近視を発症しやすいと言われています。太陽の光による明るい屋外で活動することが近視を防ぐことにもつながります。
通学で外を歩く時間もいいですし、体育の授業で外に出るのもいいでしょう。
そのほか、公園遊びや散歩など屋外活動を増やすことで近視の予防効果があると考えられています。
まとめ:子どもの近視抑制のための最適な治療と予防を選ぼう
近視は網膜よりも手前で焦点が合うことから“遠くがぼやける”状態です。
近年、
・ゲームやタブレットを連続して長時間やる
・屋外であまり遊ばない
・睡眠時間が短め
といった生活環境が一般的になり、昔よりも視力が低下している子供が増えています。
子供の頃の視力低下を見逃さずに適切な治療や対策をしていくことは、将来の近視進行抑制につながります。視力低下しているのに何もせずに成長すると近視が重症化し、将来的に目の病気を発症することもあります。
子供たちの大切な目と健やかな成長を守るため、見えにくそうな様子を見かけたときは眼科受診をしましょう。

監修者
武長眼科 院長
2001年5月15日に、小田急相模原、東海大附属相模中学・高校の正門前に開業し、
眼科の一般診療(含コンタクト)を行っております。
地元の皆様の「眼の健康」をお守りするお手伝いを、と思っています。
私たちは地域の方々の健康を最優先に考え、地域医療に貢献するため日々診療を行っております。
【資格】日本眼科学会専門医
【所属学会】日本眼科学会